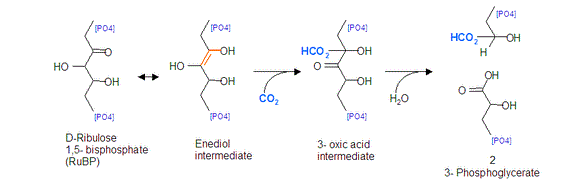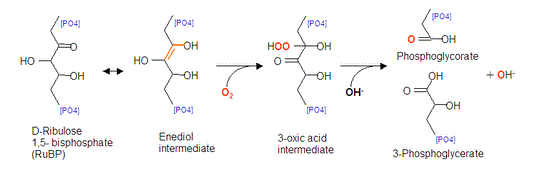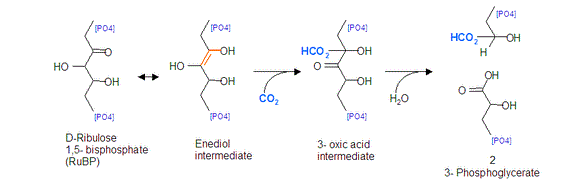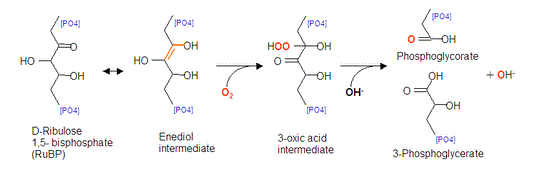「光合成」、というのは、二酸化炭素CO2、という炭素数1の化合物、「C1化合物」、と、水、いずれにしても非常に「単純」な構造の物質を原料として、最終的には、地上のあらゆる生き物がそれに依存するところの、糖C6H12O6、なる、炭素数6の「C6化合物」、非常に「複雑」な構造を作り出す過程だから、「エントロピー減少」過程であり、かつ、「吸熱反応」であった。
ΔG=ΔH-TΔS
において、「エンタルピー変化量ΔH」は「吸熱」だからプラス、「エントロピー変化量ΔS」は「エントロピー減少」だからマイナス、「絶対温度T」は、常温として、300K程度のプラスの一定値であるから、左辺「自由エネルギー変化量ΔG」は、プラスの値にしかなり得ず、これは、決して、「放っておいては」起こりえない反応であって、では、このような反応を、「無理矢理」にでも生じさせるには、「系」の「外」からの、この「自由エネルギー」増加分を補って余りある、潤沢なエネルギー供給が不可欠なのであり、それを実現しているのは、まさに、「地球」という「系」の「外」にあって、この「系」内部で行われるところの諸反応におけるエネルギーのやり取りとは、比べものにならないほどの、文字通り、「桁外れに」大きな、素人の試算(「太陽のみに、許された、力。」2011/03/27)によれば(笑)、6桁ほども異なる、「核融合反応」に由来する、「太陽」からの、「光」エネルギーの定常的な供給なのであった。「安く買って、高く売れば、儲かるじゃないか?」くらいのことしか考えなかった(笑)、「重商主義者」たちに対して、いや、この世の「富」の「源泉」は、私たちの「食べ物」を生み出す、「農業生産」、すなわち、「光合成」による「糖」生産、以外、あり得ないではないか?、ならば、その根幹には、私たちの「理知」なり「商才」なり、そんなものによっては如何ともしがたい、まったく「外的」な存在、「人類」などというもの、それどころか、地球上のあらゆる生命の存在期間よりもはるかに長い時間に渡って、ということは、私たちにとって、それを、定常的に与えられた、「所与」のもの、と見るしかできないのだが、そう(笑)、「太陽」によるエネルギー供給がある、と言わざるを得ないではないか?、と、おそらく生真面目に、考えたのが、「重農主義者・フィジオクラット」だったのであり、そして、彼らは、この、太陽による、無制限、無条件の「恵み」を、「純粋な自然の贈与・don_pur_de_la_nature」と名付けたのである、英語で言うならば、「pure_donation(gift)_from_the_nature」とでもなるだろうか、もちろん、そんなことを私が知っていた筈はなく、「純粋な自然の贈与」中沢新一(講談社学術文庫)、による、わけであるが(笑)、で、その「光合成」を、「収支」としてみれば、
6CO2+6H2O→C6H12O6+6O2
という、シンプルな一行の反応式に要約されてしまうのだが、これは、「糖」に、文字通り、火をつけて燃やし、「雲散霧消させた」という、明白な「エントロピー増大」かつ「発熱」反応、
C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O

の左辺と右辺を入れ替えただけで、それを言うだけでは、「光合成」について、何も「わかった」(笑)ことにはなっていない、ことは、知っていた。「億」の単位の年月をかけて、「突然変異」と呼ばれる確率論的過程を夥しく蓄積して、緑色植物が、組み立てて来た「反応系」は、しかし、まことに凡庸な表現であるが(笑)、想像を絶するほど複雑であって、大学生や高校生向けの教科書を開いてみても、圧倒的な数の「カタカナ」、「アルファベット」の略字、の、物質名が溢れ返っていて、到底読み進むことができず、その都度、ため息をついて、ページを閉じていたわけであるが、え、しかし、このまま「知らずに」、死んでいくつもりか?、と、「還暦」を目前に(笑)思い立ち、そう、「六十の手習い」、まずは、少なくとも、C1からC6への、炭素数の増加、の過程だけでも、追いかけてみたい、と思ったのだ。きっかけは、うちの屋上「菜園」のプランターに、繁殖している、キンチョウ(ベンケイソウ科)、が乾地に適応した、「CAM光合成(Crassulacean_Acid_Metabolism)」という特別な光合成回路をもっていることを、説明したい、と思い、しかし、では、「特別でない」光合成システムについて、お前には語るべきものがないではないか?、と思い至ったから(笑)、であった。CAMは、「ベンケイソウ科型・酸・代謝」の頭文字(acronym)であり、そのCで始まる語は、ベンケイソウ科、のラテン語学名の、多分、形容詞形、なのであるが、他にも、「暖地」である当地には、熱帯性の植物であるサトウキビ(イネ科)、など、「C4植物」が存在する。これは、「通常の」光合成システムが、まず、炭素数3の化合物を作ることから「C3植物」と呼ばれるのに対立した言い方なのだが、では、はじめてみよう(笑)。「光合成」の基本的な回路、発見者の名を冠して「カルヴィン回路」と称するが、カルヴィン氏は確かイギリス人だからそうなのだが、Calvinはフランス語読みならカルヴァン、あの、「資本主義」に精神的支柱を与えた、ことになっている、プロテスタント指導者の名前、なのであった、・・・、閑話休題、そこでは、C5化合物が、二酸化炭素を受け取り、C6となるがただちに二つのC3に分解、それらのうちごく一部が、合成されてC6の「糖」となり、それ以外は、再び、複雑な修飾をうけて、C5化合物として、循環する、という、長い物語になっている。「できる範囲で、かまわないから」(笑)、それを、追跡してみることにする。私が、「生まれて初めて」、路傍の野草に目を向け、その「名」を知り、いや、そもそも、その「名」を「知りたい」と思ったのが、ようよう、たった十年前、なのである。それまでの五十年間、私は、植物が否応なく「目に入り」、また、食糧として食べていたにもかかわらず、「彼ら」について、何も「知り」たいとは思わず、「知らなく」ても、不都合とは思わずに、生きてきた。人が、「知らず」に済ませていられるのは、何故か?、はっきりしている、それは、「知りたくなかった」、からだ。「知る」、ことは、「返礼」を要する「贈与」、なのである。「贈与」を受けた者は、受けたものよりもより価値の高いものを、「返礼」として贈り返す「義務感」に苛まれることになる。それが煩わしい、と思った人達は、「他者」の言葉が聞こえてくる度に耳をふさぎ、「悲しい話を聞かせないで!」と絶叫し、絶叫するのは、「相手」よりも大きな声を出すことで、「聞こえない」ようにするためだ、これを音響学では(笑)「マスキング」と呼ぶ、または、「相手」が話し始めるよりも前に、「私はね、・・・」と、自ら語り始めることで、「相手」を、黙らせるのだ(笑)。