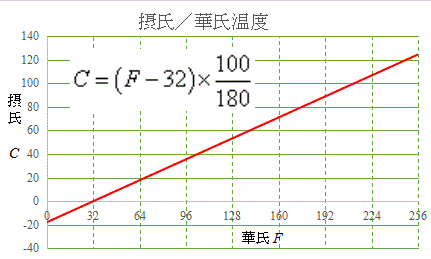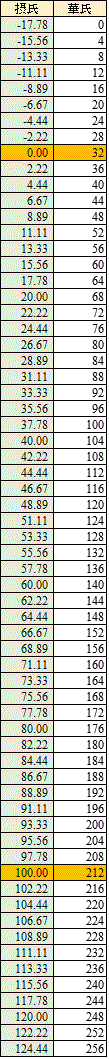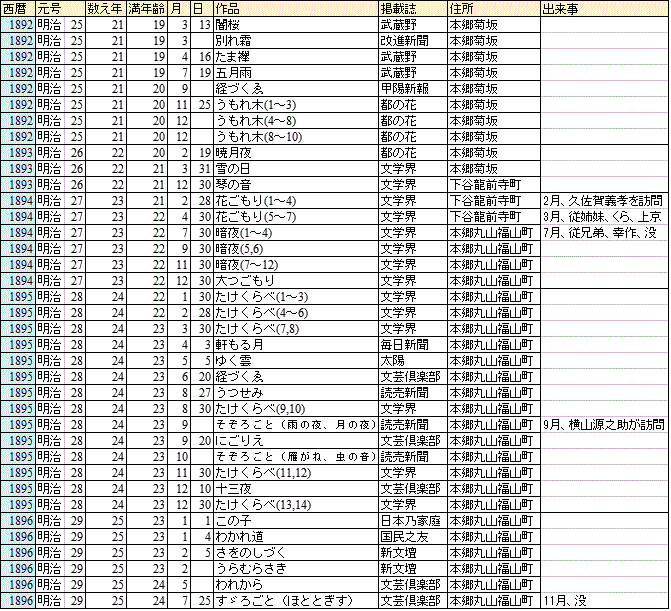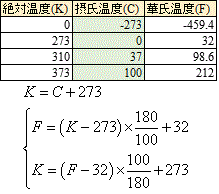ファーレンハイト氏はダンチッヒの人、「ブリキの太鼓」の舞台の街であるが、18世紀初頭、そこがドイツ名ダンチッヒと呼ばれる街であったのかポーランド名グダンスクであったかは複雑な問題である。1569年ポーランド・リトアニア共和国に併合、1806年ナポレオンによる征服、1807〜1815自由都市ダンチッヒ、1815年ウィーン会議にてプロイセン領、ヴェルサイユ条約後1920〜1939自由都市ダンチッヒ、1939年ナチによりドイツへの編入。ギュンター・グラス「ブリキの太鼓」は、このナチの侵入から、1945年赤軍による解放、までの期間が描かれている。ファーレンハイト氏は、1708年か1709年の冬の日、当地で記録された極めて低い気温を0度に、また、自分の体温を100度と設定して温度目盛りを考案した。水の凝固点/沸点をそれぞれ0/100とする摂氏温度(セルシウス)と比較すると、水の凝固点が32F、沸点が212F、したがって、変換式は、
C/100=(F-32)/(212-32)
摂氏より1.8倍「細かい」目盛となる。ThirdWorldに96°Fという曲があって、
96 degree in the shade, real hot even in the shade
96度、日陰でも、十分、暑い
ジャマイカのキングストンは、今調べてみると(笑)、北緯18度、まがうことなき熱帯である。
(96-32)×100/180=35.56
確かに、日陰でも、暑かろう。亜熱帯の当地でも、想像は、出来る。
(100-32)×100/180=37.78
であるから、ファーレンハイト氏のその日の(笑)体温は、やや高めであったことになる(笑)。
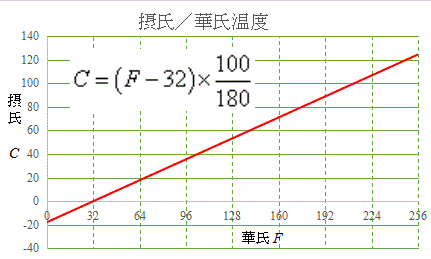
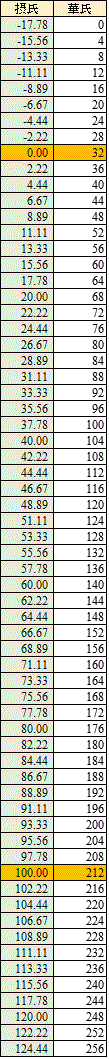
山川菊栄「武家の女性」(岩波文庫)に、病に罹った「嫁」が実家に「帰される」例として徳富蘆花「不如帰」が挙げられているので、「青空文庫」を無料download、退屈さをこらえて(笑)、何が「退屈」なのか?の考察は、後ほど(笑)、読み始めた。浪さんの海軍士官の夫が香港からの手紙に「華氏九十九度」が登場したから、計算してみたまでだ。
***
二十七日。晴れなれどもすずし。すずしといわんよりは冷ややかなる方なり。二十四日の寒暖計、正午九十三、四度とありしに、その夜より下りに下りて、二十五日は七十度より八十度、夜に入りては六十度にさえなりぬ。昨日も今日も七十度代なり。
「塵の中」樋口一葉(ちくま日本文学「樋口一葉」所収)
「塵の中」は、明治二十六年(1893)七月から八月の日記に付された名である。吉原遊郭門前の下谷龍前寺町に引っ越した直後だ。摂氏温度に換算した上(笑)、現代語訳を試みよう。
二十七日、晴れだけれども涼しかった。涼しいというよりは、むしろ冷たいぐらいだ。二十四日の温度計の目盛は、正午には、三十四度だったのに、夜になると下がりに下がって、二十五日は二十一度から二十七度、夜には、16度にさえなった。昨日も今日も、二十度台。
(93-32)×100÷180=33.89
(94-32)×100÷180=34.44
(70-32)×100÷180=21.11
(80-32)×100÷180=26.67
(60-32)×100÷180=15.56
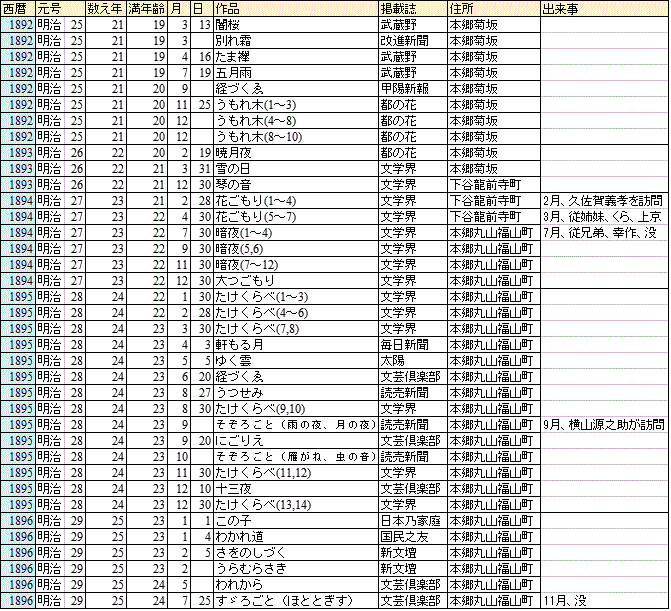
***
こうしてみると、日本においては、明治時代には、華氏温度が日常的に用いられていたであろうことが窺われる。「海軍」はいざ知らず、樋口家の寒暖計の目盛がそうだったのだとすればね。摂氏温度が「国際単位系(SI)」に採用されたのが1948年、水の沸点・凝固点という物理学的事実に根拠を置いているから、こちらの方が、科学技術的な記述には向いていたであろう。「絶対温度(ケルビン)」も、摂氏と同じ目盛幅を採用している。元物理・化学教師としても、すべての分子が熱振動を停止する、といわれている(笑)、絶対零度がマイナス459.4Fだ、などということを改めて記憶しなければならないのだとしたら、今さらうんざりするが(笑)、ただそれは、私たちが、摂氏の日常に馴染んでいるからに過ぎないだろう。
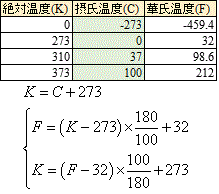
なるほど、華氏ならば、この、樋口一葉を読んでも納得できるように、日頃言及される気温は、ほぼ間違いなく、ことごとくゼロと百の間に収まるのである。